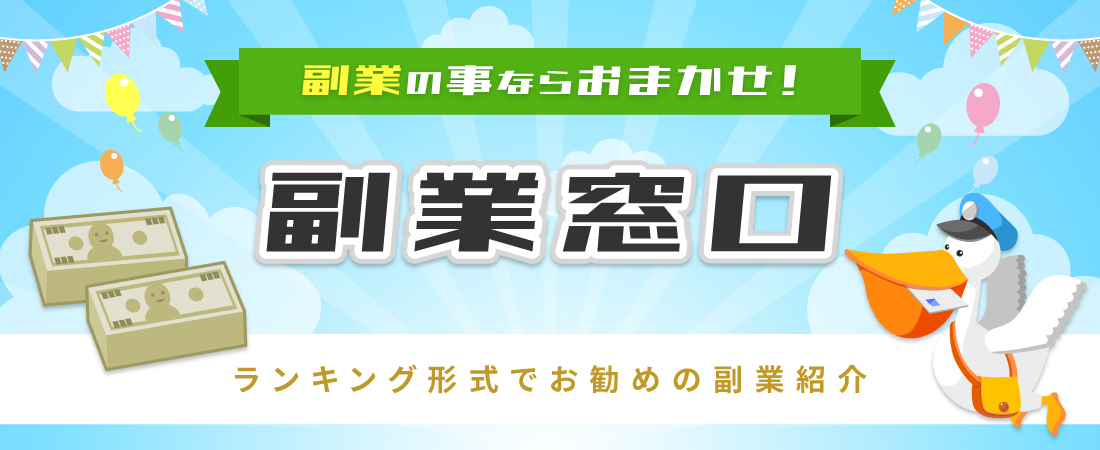育児休業中の働き方の基本ルール
育児休業中は、基本的に育児に専念することが前提です。育児休業制度は、休業期間中の労働義務を免除することを目的としており、この原則があるからこそ、働かなくても解雇されることがありません。
ただし、例外として「一時的で必要最低限の範囲」であれば、休業中でも働くことが認められています。具体的には、月10日以内または月80時間以内であれば、育児休業給付金の支給対象として扱われます。
一方で、たとえ上記の範囲に収まっていたとしても、「毎週決まった曜日・時間に働く」というような定期的な勤務は、一時的・臨時的とは認められず、給付金が停止される可能性があります。
育児休業中の副業収入は給付金に影響しない
育児休業中に影響するのは、「育児休業を取得している会社からの給与」です。副業で得た収入は、育児休業給付金の減額対象にはなりません。
ただし、育休中に本業先で働いた場合、給付金と給与の合計が賃金月額の8割を超えると、給付金が減額されます。一方、副業は給付金に一切影響しないため、働きたい場合は副業の方が調整しやすいと言えます。
とはいえ、最優先すべきは育児です。働く場合も、無理のない範囲で行うことが大切です。
お金を守る力の重要性
お金に関わる5つの力(貯める・増やす・稼ぐ・使う・守る)の中で、最も軽視されやすいのが「守る力」です。しかし実際には、どれだけ稼いでも、どれだけ増やしても、失ってしまっては意味がありません。
詐欺手口は年々高度化しており、若い世代の被害件数も増えています。自分には関係ないと思っている人ほど、知識不足が原因で被害に遭ってしまう可能性があります。
また、金融トラブルや不正アクセスなど、お金を失うリスクは身近にあります。リスクを避けるには、「最新情報を学び続ける姿勢」と「仕組みで守る」ことが欠かせません。
家計管理の基本:予算の立て方
良い予算は、豊かな生活を作る基盤です。予算を立てるためには、まず以下の2つの事前準備が必要です。
- 収入の把握(手取り月収・年収)
- 支出の把握(家計簿アプリでデータ化)
支出把握のためには、現金払いを避け、キャッシュレスを活用してデータを自動取得することが重要です。
予算の立て方の3つの方法
① 収入の◯割方式
収入の8割や9割を上限として暮らす方法です。シンプルで分かりやすい反面、自制心の弱い人は予算オーバーしがちです。
② 前期比◯%方式
前月または前年の支出を基準に、一定割合の削減を行う方法。年々貯蓄率が上がるメリットがある反面、息苦しさを感じる場合があります。
③ ゼロベース方式
すべての支出を一旦ゼロとして、本当に価値のある支出だけを積み上げていく方法。最も本質的ですが、判断力が必要なため上級者向けです。
おすすめの予算管理:「固定費×変動費」の組み合わせ
上記3つの方式の“いいとこ取り”として、以下のステップを推奨します。
ステップ1:固定費の最適化
住居費・通信費・水道光熱費・サブスクなど、契約によって決まる固定費を見直します。最適化できたら、毎月の細かい管理は不要です。
ステップ2:変動費の最適化
変動費は「合計でいくら使うか」を意識し、項目ごとの細かい予算を作りすぎないことがポイントです。都度「これは価値ある支出か?」と自問して判断します。
ステップ3:定期チェック
- 固定費:年1回見直す
- 変動費:月1回振り返る(満足度と貯金額を確認)
年間で手取り収入の2割以上貯金できていれば優秀です。
まとめ
育児休業中の働き方、社会保障の知識、お金の守り方、そして家計管理。どれも生活に直結する大切なスキルです。特に予算の立て方は人生の満足度に直結します。自分に合った方法で家計を整え、安心して暮らせる基盤を作っていきましょう。