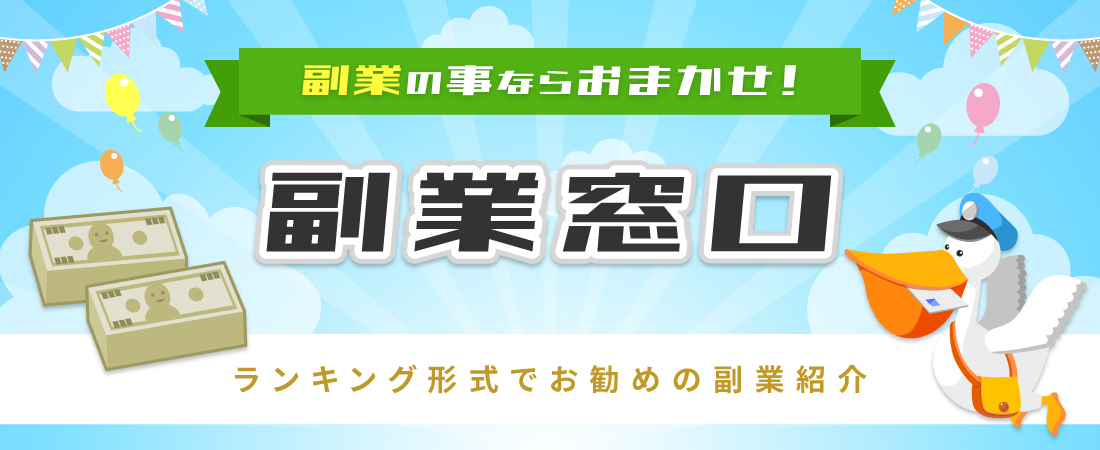育児休業中の社会保険料免除ルールとは
育児休業中は、社会保険料が免除される特別ルールがあります。この免除とは単に「払わなくてよい」というだけでなく、「払ったことにして扱われる」ことも含まれます。つまり、保険料を支払わずに保障を受けられる非常に手厚い制度です。育休を取得予定の方は、この制度をフル活用することが大切です。
育休の取得期間と社会保険料免除
実際に育休を取得した人の傾向として、男性は短め(3か月未満)が多く、女性は1年以上の取得が多いです。しかし、短期間の育休では保険料免除の対象外になるケースがあります。そのため、育休を取得する前にルールを確認することが重要です。
免除の対象となる保険料
育休中に支払いが免除される保険料は、健康保険料と厚生年金保険料の2つです。原則として、育休を開始した月から職場復帰した月の前月までの保険料が免除されます。
例えば、育休開始日が8月10日で、12月9日に職場復帰した場合、8月から11月までの4か月分の保険料が免除されます。また、月末に育休を取得していれば、その月も免除されます。
短期間の育休と免除ルール
短期間の育休の場合、以下の条件で免除の適用が決まります。
- 月末を含む育休: 休業日数に関係なく、その月の保険料は免除されます。
- 月末を含まない育休: 休業日数が14日以上であれば、その月の保険料が免除されます。13日以下では免除されません。
このルールを知らずに育休期間を決めると、受けられるはずの免除を逃してしまう可能性があります。
ボーナス月の育休について
以前は、ボーナス月の月末に短期間の育休を取得すると社会保険料が免除されるケースがありました。しかし現在は、ボーナスに対しては1か月以上の育休を取得しなければ免除されません。法制度には変更があり、適用条件を正確に確認することが重要です。
まとめ
- 育休中は、月末に休業している月の保険料が免除される(月末ルール)。
- 月末を含まない短期育休の場合は、14日以上の休業で免除される(14日ルール)。
- ボーナス月は1か月以上の育休を取得しなければ免除されない。
育児休業中の社会保険料免除は、子育て中の家計にとって非常にありがたい制度です。複雑なルールもありますが、基本を押さえて計画的に育休を取得することで、制度の恩恵を最大限活用できます。